山城直樹はポーカーで巻き上げていた
直樹は、ウォール・ストリートの証券外務員のように実直な性格でありながら、ポーカーで生計を立てる型破りな人物だった。毎朝きっちり七時に目を覚ますと、ジムでのワークアウトを済ませ、シャワーを浴びてカジノに出勤するのが日課だった。一日八時間、決まったテーブルに着席し、確率と統計にしたがって淡々と仕事をこなした。直樹は自身のことを、流れてくる伝票を処理する事務員のようなものだと考えていたが、顧客(鴨)にされた中華系の富裕層からすれば、運悪くテロリストに襲われたようなものだった。
本職をギャンブラーとしながらも、(意外なことに)直樹は素朴で丁寧な暮らしを好んでいた。タイ湾に浮かぶココナッツ・アイランドで、プール付きのコンドミニアムに住んでいたが、その暮らしぶりは模範的市民のようだった。開業届けも確定申告もきちんと提出していた。間違ってもブランド品で身を固めたり、高級時計を見せびらかすようなことはなかった。地元のバーで女の子を口説き、星空のもと波の音を聴きながら、安いビールを飲めればそれで十分だった。実際に直樹と会うときにはいつも、地元民しか知り得ない場末の店で、とびきり美味しいビールを飲ませてくれた。
いったい、どんな教育を受ければ彼のような人物が出来上がるのだろう。不思議に思った私は、彼の地元を訪ねることにした。直樹は「わざわざ来ていただくほどのものはありません。特筆すべきものは車海老の養殖場くらいですから。」と謙遜したが、そこは東洋一美しいと称される球美の島があった。澄んだ海はエメラルドで、白の砂浜はホワイト・トパーズ、夜空にはブラックオパールとダイヤモンドを思わせる銀河が広がっていた。そのあまりの美しさに見惚れ、(気づいたとには)私は画面を持つ電子機器を余すことなくリサイクル・ボックスに収めていた。この情景を前にスクリーンを見るというのは、今まさに天使が空から降りてきて美しいハープを奏でようとしている時に、テレビの再放送番組を見るような気持ちになったからだ。
島のビールを浴びるほど飲んだ翌日、私は夕暮れまで水平線を眺めていた。私が成績表の順位を気にしていたころ、直樹は地球儀をまわし、海の向こうに恋焦がれていたのだ。私が東京か大阪、どちらへ上京するかを悩んでいたころ、直樹はラスベガスかモナコ、どちらで巻き上げるかを考えていたのだ。やはり私の悩みなんてミジンコみたいなものである。
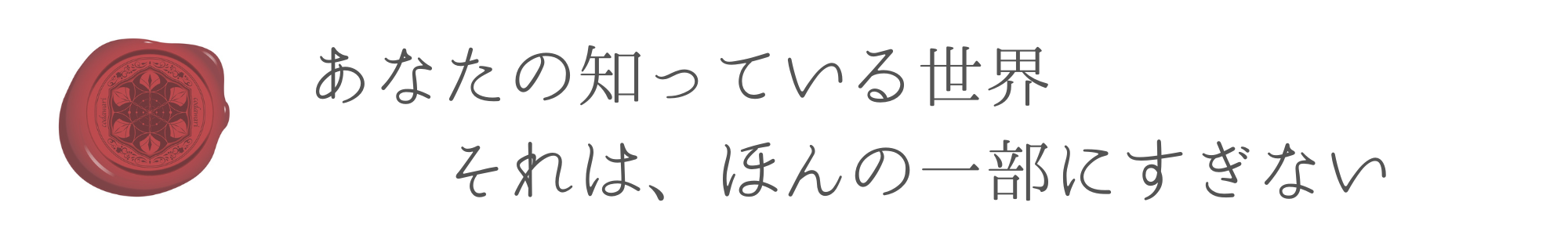
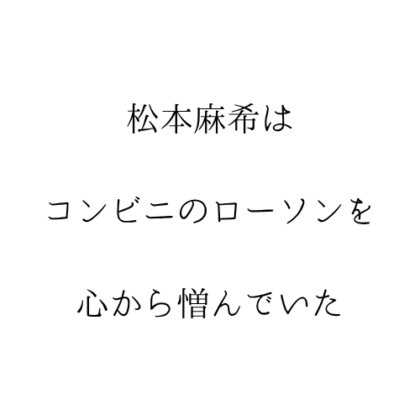
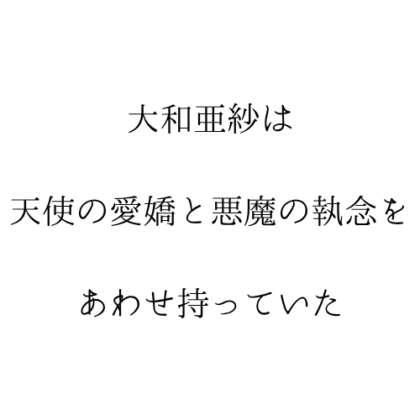
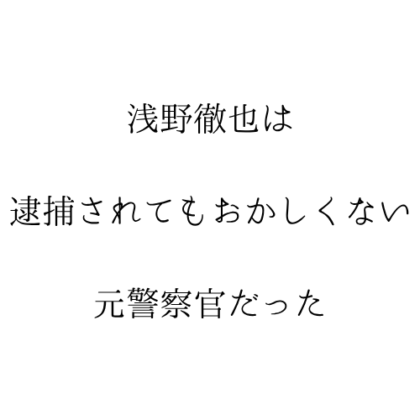
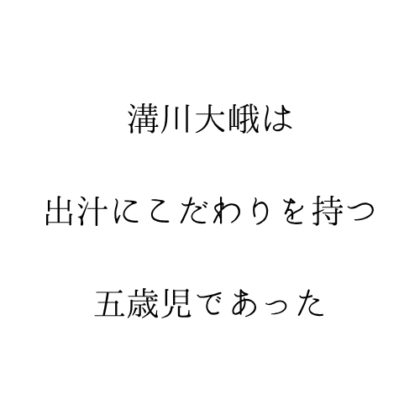
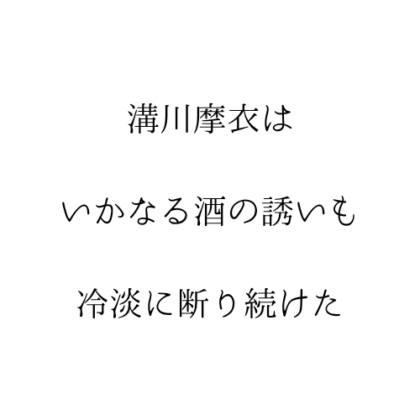
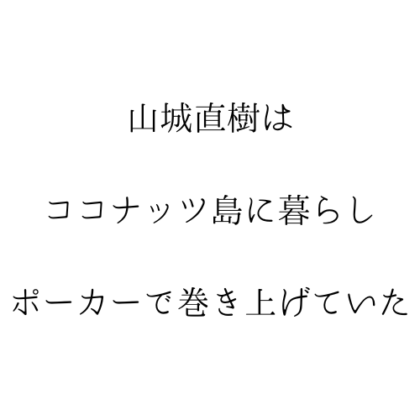
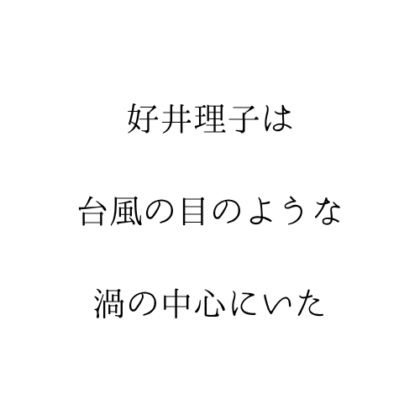
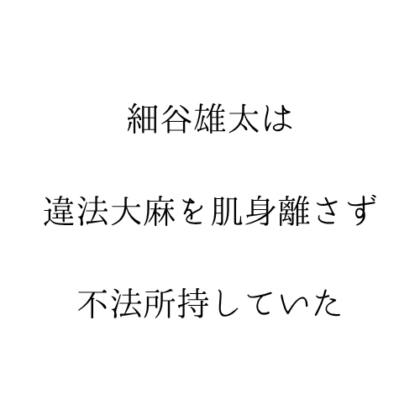
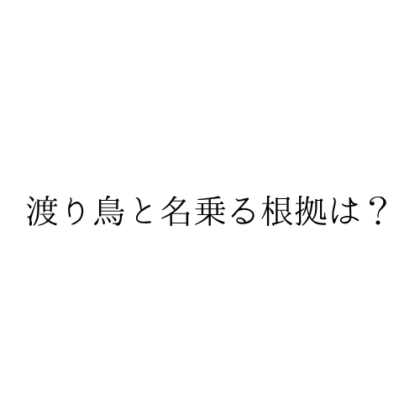
感想を記す